|
|---|
2025年6月28日(土)  国の重要文化財(S59)大滝神社本殿 |
|
日本一複雑屋根の大滝神社は、2018年6月「鬼ヶ岳~蛇ヶ嶽」の登山後に訪れています。最近、そこから裏山を周回できることを知りました。 その大徳山はお楽しみポイントが多く、大滝神社、奥の院、ブナ林、大スギ、展望台と低山でも充実しています。 北陸自動車道武生ICで下り、r262~r200東の和紙の里公園へ走ります。教科書は「岡太神社・大瀧神社パンフレット」です。 |
駐車場 ドラッグスクロールで移動 大きい地図 |
※赤線はGPS軌跡 ●は主な分岐点 |
| 江南発:午前7時30分 曇り/25℃ 駐車場:午前9時45分 曇り/26℃ 高低差:276m(50m→326m) |
往:1時間35分(山頂まで、小休止含む) 還:1時間00分(ランチタイム除く) 所要時間:2時間35分 |
||||||
 大滝神社の日本一複雑な波打つ屋根です。背後の山と調和がとれいつまでも見ていられます。 しかし、屋根の一部は鉄板で覆われ、桧皮葺(ヒワダブキ)が傷んでいました。 |
|||||||
 拝殿を済ませ神社南の駐車場に戻り、リュックを背負います。西へ30m歩けば… (10:25) |
|||||||
 石灯籠のY字分岐があり左坂へ。 |
|||||||
 幅広の参道を登ります。なぜこんなに広いのか? (謎解きは道草で) |
|||||||
 途中、展望台が立ちます。さてさて眺望は… |
|||||||
 残念なことに枝が伸び、窓から西に左:鬼ヶ岳533m、右:蛇ヶ岳418m、白い直線は北陸自動車道です。 (10:45) |
|||||||
 やがて奥の院に。天狗は、山岳信仰で欠かせない守護者です。家には怖くて飾れません。 |
|||||||
 奥の院拝殿(江戸中期)に着き、石段を登ります。山頂ルートは、拝殿の右です。 (11:15) |
|||||||
 大滝神社・奥の院本殿(市指定文化財)/江戸中期。 |
 奥の院・岡太神社本殿(オカモト/市指定文化財)/江戸前期。 |
||||||
 拝殿から東南30mでY字分岐。左を取り、尾根を目指します。 (11:20) |
|||||||
 斜面には、ぶっといブナがゴンゴン並ぶ。雪が少ないエリアで、ブナは背が高く30mはあるでしょうか。 |
|||||||
 主尾根に乗り、北西へ進むと突然、するどい切れ込みの堀切。ここは2つ目の堀切で、右に階段があります。 |
|||||||
 そして広い平坦地の大瀧城本丸跡。「大滝神社の大スギ」がすごい枝ぶり。 根周り9.8m、高さ23mの老樹です。(県の天然記念物) (11:40) |
|||||||
 ここは信仰の山だとは知っていましたが、城址とは知りませんでした。また堀切です。 |
|||||||
 大徳山326m三等三角点。北に切開きから眺望が有ったと思われます。枝で隠れました。風が通りランチします。 (12:00)~(12:45) |
|||||||
 西尾根で下山。そういえば、神社で宮司様がクマは見ないけど、カモシカはいると教えてくれました。 |
|||||||
 三叉路分岐です。「大滝」から来て、西の「岩本」へ降ります。北西は、「定友」へのです。 (12:50) |
|||||||
 「大滝」は幅広参道でしたが、「岩本」ルートは階段参道です。延々と続きます。 |
|||||||
 秋葉山展望台(標高70m)に出て、ようやくすっきりした眺望が得られました。 田圃との標高差は45mです。集落には越前和紙の里会館が建ちます。 右端奥:鬼ヶ岳533m、その左手前:村国山239m。 (13:20) |
|||||||
 大滝神社に向かって舗装道を歩きます。西鳥居から境内に入り、もう一度日本一複雑な屋根を鑑賞しました。 (13:45) |
|||||||
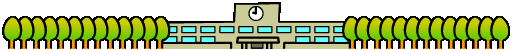 東海岳行 |
|||||||
好運にも大滝神社境内でお掃除をしていた宮司様(多分)とお話しができました。まずは、「日本一複雑な屋根」を撮るベストポジションへ案内して頂きます。私の疑問で「いつ・誰が・目的で何か・資金は?」などをお尋ねしました。 大滝神社の創建は1500年前ですが、今の社殿の建立は天保時代です。設計は永平寺の名棟梁・大久保勘左衛門。拝殿は別に建っていたのですが、本殿と合体させた複合社殿に再建しました。本殿下に石を重ねかさ上げします。(下左)
しかし、そのままでは屋根のバランスが悪く、棟梁は手前から3番目と4番目を追加して、全部で5つの屋根にしました。(上右) 工事は1843年。1833年~1839年に「天保の大飢饉」が起き、1841年~1843年に「天保の改革」が実施された頃です。 この辺りは、越前和紙で栄え、資金は賄えたようです。今の社殿は33根前に修復されましたが、桧皮葺(ヒワダブキ)の傷みがひどく葺き替えを近々行います。費用は1~2億円で、国と自治体が大方補助しますが、地元負担は1割です。
1口500円から、下山後賽銭箱に納めました。社殿には素晴らしい木彫り彫刻があり、正面に獅子・鳳凰・草花、側面には中国の故事を題材にした丸彫りの彫刻と凝っています。木彫り装飾は、滋賀の職人を呼んで造ってもらいました。 社殿右の神輿殿に金箔の貼られた豪華な神輿が4台格納されています。毎年5月5日は「神と紙のまつり」が行われ、重い神輿を担ぎ地区を練り歩く。(下右) 夜、神輿は地元の人と観光客で奥の院まで登り、神様は山にお帰りになります。
それで神社から奥の院までの参道は広く作られていたのですね。 |
|||||||






