2012年1月18日(水) -小牧「市民四季の森」展望台から北の小牧アルプスを望む-  左に白煙の環境センター、煙突の右ピーク白山がアルプスの西端でその右へ白山神社と続き 右方で大きく一番高く見えるのが本堂ヶ峰、右端ピークが天川山、カメラを更に右へ振り‥  左から本堂ヶ峰、鞍部の右に天川山、東天川山、東山(写真中央)が三段に並び 右のアンテナが安手奈山でアルプスの東端。東の白山から西の安手奈山まで直線で2.2kmです。 |
|
『尾張一の大展望地に行きましょう』いつも近郊低山の好奇心溢れるルートをご案内して頂く野良人さんからの知らせが届きました。 その場所は、小牧アルプスの途上にあるそうです。各務原アルプスは知っているけど小牧アルプス?恥ずかしながら私は知りません。謎です。行かねばなりません。 小牧市白山一帯を整備して1995年10月にオープンした「ふれあいの森」から歩き始めます。野良人さんの山仲間Aさん、Oさんもご一緒です。 車は、施設の南側にある温水プール駐車場を目指して走ります。 |
<駐車場> [-]広域図、[+]詳細図、ドラッグスクロールで移動 |
温水プール駐車場→コモウセンゴケ群落→兒の森入口→▲本堂ヶ峰→▲天川山→展望地→▲東天川山 →▲東山→ドコモ中継所→▲安手奈山←▲西山→兒の森入口→展望台→温水プール駐車場 ※赤線はGPS軌跡 ※黄○は主な分岐 ※▲ヲンナゴロシ209mは「愛知アルプス山行記」さんより ■「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平17総使、第98号)」 |
||
| 江 南:午前9時05分発 晴れ/0℃ 駐車場:午前10時00分着 晴れ |
安手奈山まで:1時間50分(以下、小休止含) 駐車場まで:1時間35分 ◆往還時間:3時間25分 |
 駐車場奥にふれあいの森入場門があります。横切るものは、右方のゴミ処理施設からプールへ供給される温水パイプです。 (10:05) 谷沿いの遊歩道を少し登ると‥ |
|
北新池に出ます。ここはトンボ王国と名付けられたビオトープ。 2000年の東海豪雨で荒れましたが復活されました。 樹冠にどっさり赤い実を付け、アピールする木の名※が分かりません。   この辺りの山域でポツポツと見ますが、ひときわ背が高い木です。 この辺りの山域でポツポツと見ますが、ひときわ背が高い木です。その上に白山神社260mの鳥居が見え、左ピークが白山224mです。 その2ヶ所は、昨年「尾張三山」で歩きましたので今日は訪れません。 ※2/23御池池守さんから「タマミズキ」とご教示いただきました。 今年は実の当たり年のようです。 |
|
 池の東に進むと広いコモウセンゴケ群落。ご存知、食虫植物で、5〜8月には5〜10cmの茎を伸ばし、淡紅色の花を付けます。 |
 今は、車輪状に拡がる葉だけです。紅色の毛で虫を捕獲します。これは3cm径程の大きなもの。市民四季の道を行き、疑似木階段を登れば‥ |
 東屋のある休憩所です。南方面の名古屋、高蔵寺市の展望が逆光で楽しめます。右端の白煙は、ゴミ処理施設です。 右でアピールしてる高層ビルは、桃花台ニュータウンの33階建てスカイステージ33。築21年で中古で1300万円です。 |
|
 1300万円は無理なので、更に四季の道を行きます。ふれあいの森東に2006年4月開園した兒(チゴ)の森入口へ到着。 「兒」は「児」の旧字体で地元の児(チゴ)神社に由来しています。左上に見えるバイオトイレから、ささゆりの道を歩くと‥ (10:45) |
|
 わくわく小屋の広場に着きました。私達は斜面を直登します。右の縁取り道は、緩やかなスロープで車椅子で上られます。 それはうぐいすの小道で、ボランティアも参加して作られました。ピークを巻いて延び、その長さは驚きます。 |
|
 尾根に出てリスの小道を進むと青空小屋があり南への展望。近くの車道でリスを見たので生息は間違いないでしょう。 その先が、境界杭と右端の古びた山名表示の本堂ガ峰山頂271m。地形図の278m地点は、青空小屋のようです. (11:05) |
|
  県有地の柵に沿って降ると兒の森の東端になります。 県有地の柵に沿って降ると兒の森の東端になります。←そこには私有地で柵が通せんぼしていました。 立入禁止表示ですが、柵に針金が無い箇所が設けられています。 所有者の寛大な気持ちに感謝して通らせていただきました。 テープがあるのでルート以外を歩かないようにします。 |
|
 そして天川山(テンカワヤマ:別名大山)282m山頂。小牧市史によれば、ここが市内最高点です。切り開きで南に展望があります。 ところが、東へ50mいくと‥ (11:15) |
|
『こ、これは、尾張一の展望だ』北面の眺望をカメラやビデオで撮りまくりました。 恵那山2191m、中央アルプス、御岳山3067m、乗鞍岳3026m、白山2702m‥目には見えますが。 カメラは3回くらい分けて撮り、つなげればパノラマ写真になります。    尾張富士275mと入鹿池が並んで実にかっこいい。 尾張富士275mと入鹿池が並んで実にかっこいい。採石場が拡がり、東端にこの展望地が出来ました。 歓喜の展望を後に天川山へ戻り、縦走を続けます。 道脇のショウジョウバカマの葉を見送り‥ |
|
 展望地から5分ほどで東天川山281mに到着。縦走路の登山道は、はっきりしてテープも多過ぎるほど付いています。(11:30) |
 小さなアップダウン・方向転換が続き、雑木林の歩きは退屈しません。主尾根のピークごとに山名表示があり、東山275mを通過します。(11:40) |
 次の山は『ア・テ・ナ・ヤマ??』『アンテナヤマでは』『なるほどね、ドコモのアンテナ近くだからか』洒落ています。 終始、登山道にあるこのラミネートの表示が案内します。西の白山224mから東の安手奈山までが、小牧アルプスです。 |
|
 一度、未舗装の林道へ出たら左に横断して山へ入ります。すると登山道に小牧アルプスの山爺です。 常緑広葉樹シイの巨木は、幹周2mくらいで樹高は20m近くあるでしょう。やがて‥ |
|
  突当たり、コンクリート壁を木の足場とロープで登れば、ドコモ東小牧無線中継局です。 展望は、あそこに登らないとダメ。それでは、フェンスにもたれてランチにします。 (11:50)〜(12:45) |
|
 フェンスの東角へ回り込み、小さく登ってピークハント。最終峰安手奈山273m(三等三角点:せん谷)です。展望はありません。 (12:50) |
|
 安手奈山から山頂北にあるJR小牧研究施設近くに降りるコース、または ドコモの中継局へ戻り、車道で帰るコースもあります。私たちは来た道をピストンです。 |
|
 兒の森へ戻り、本堂ヶ峰のリスの小道を行き、きつつきの小道へ入ります。 (13:30) |
 数分でこの西山277mピークです。50段階段を降り、うぐいすの小道でわくわく小屋へ到着。まほろばの里山通りから兒の森入口へ帰りました。 |
 ふれあいの森に入り、紅葉の森を歩きます。道脇の石壁を見て『これは造り物だ』『いや石積みだろ』と首をひねる。 よく見ると同形の石が順列を作っていました。良くできています。森内のダムや土砂止めにも使われ、繊細な土木技術です。 |
|
 早春の森を通り、野鳥の森の展望台へ行きます。以前は、樹木が伸び眺望がありませんでした。 早春の森を通り、野鳥の森の展望台へ行きます。以前は、樹木が伸び眺望がありませんでした。その頃、高蔵寺のP氏が白山神社の北側をコンコンと切り開き、白山2702mと御嶽山3067mが望めるようにしました。 当然、神社側にとがめられ、次にこの展望台南東側を切り開いたそうです。 (14:10) ※展望台から北へ行けば、小牧アルプス西端の白山です。 |
|
 温水プール駐車場へ戻る途中、野良人さんは遊歩道を外れ昔の登山道に入りました。道はバリルート化しています。 温水プール駐車場へ戻る途中、野良人さんは遊歩道を外れ昔の登山道に入りました。道はバリルート化しています。すると木に古びた小牧アルプスの表示が「温水プール・展望台」を示しています。  アルプス出発はこの道だったのか。 アルプス出発はこの道だったのか。やがて入場門西側に出ればもう駐車場です。 (14:25) |
|
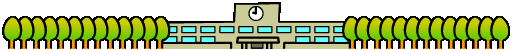 東海岳行 |
|
朝はパン食です。お財布に優しいマーガリンを塗り、身長を伸ばしたいので牛乳を飲みます。それと善玉菌を増やすヨーグルトは欠かせません。食物繊維を取るためナタデココ入りです。そしてビタミンCがタップリ詰まった安い果物とバランスの良い朝食をします。 戦後の米国が仕掛けたパン食推進作戦にまんまと乗ったというわけです。ここに滋養強壮のためニンニク卵黄、皇潤があれば言うことなしですが、欲を言えばきりがありません。さて以前、喫茶店で食べたトーストが、余りに美味しいのでマスターに家庭との違いを尋ねました。 パンは業務用でマーガリンではなくバターが塗られています。オーブントースターがこれまた業務用ですが市販品とどこが違うのか。それはヒータが大きく、匡体全体に熱容量があるのです。焼いてる時、温度調節のためヒーターは点いたり消えたりします。  その入り切りの時間が短く、素早く温度を回復でき、安定した温度で焼けるのが業務用です。一般用と比べ安いのでも7000円から2万円と価格は当然きつい。業務用の食パンは買えないので市販で一番売れた食パンを調べます。敷島製パンの超熟食パン6枚145円だということが分かりました。 そのこだわりは「甘味、原料厳選、添加物未使用、和食に合う」です。発売して13年のロングラン商品で40%もシェアを取っています。因みに2位はフジパンの本仕込食パン6枚でした。美味しく食パンをいただくには、お金に糸目をつけずこれらを揃えればいい。 ところで食パンはちょっと高飛車君です。アンパンやジャムパンも食べられるパンですから食パンと思います。だから食パンを四角パンとか、トースト用パンにすれば対等となります。食パンの由来は?美術では、食パンを古くからデッサンの道具として用いていました。  木炭デッサンにおいて消しゴムは硬くて紙を傷めるために使用できません。柔らかく油分の少ない食パンを代用しました。この時に使うパンを消しパンと呼び、食用のパンを食パンと呼ぶようになった説があります。 現在では明治初期に外国人の「主食用のパン」であることを示すために定着したというのが一般的です。ところで食パンの袋を閉じるジグソーパズルのピースみたいなプラスティックの留め具がありますが、私の嫌いなものの一つです。 あれは扱いにくく、ひねっても中々上手く外せません。はめるときは、もっと難儀で『あ〜ややこしや!』とイライラします。テレビ番組で見たのですが、関東のメーカーが70%のシェアがあり、名前はそのまんまクローザーというそうです。  番組で外し方を説明していました。左写真のように指2本をクローザーの下に当て上手前に上げればスーッと外れます。はめるときは、右写真のように指をクローザーの上に当て、下におろせばスコッとはまります。 消費者の方は、ご存知だったのでしょうか。いずれにせよ永年、悩んでいたことがやっと解決しました。お陰で今は快適に食パンを袋から取り出せています。さ、美味しいものを一杯たくさん食べ長生きしましょう。 |
|
